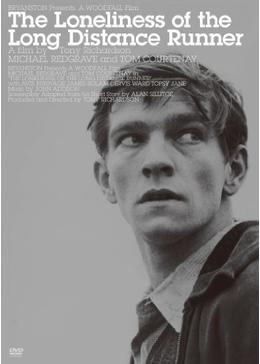小学生のころ、「せんせい、あのね。」ではじまる日記のようなものを、ほぼ毎日、書いていた。当時の担任だった須山先生というベテラン女性教員は、国語が専門であったこともあり、日記の添削というのか、子どものつたない言葉からあふれ出る何かを、とても上手にキャッチしてくれる達人だった。
とにかく、毎日のように「せんせい、あのね。」を書いた。内容はほとんど、季節(花や気候など)に関する気づきや、家庭での出来事、習い事の報告などだった、と記憶している。
たとえば、秋。金木犀がアスファルトに落ちているのを見て、「道ろが、オレンジ色のじゅうたんのように見えました」と書けば、その表現に赤字で一文字ずつマルをつけて、余白に「とてもきれいな表現ですね。先生は、まやちゃんのそういった視点が好きよ」と書き加えてくれた。そして、そんなふうによく書けた日は、花まると、それから特別よかったときには金色の丸いシールもペタリと貼ってくれたのだった。
その花まるや金色のシール、なにより先生からの“肯定の言葉”が嬉しくて、わたしは、おそらくクラスで一番のペースで「せんせい、あのね」を書き続けた。いま思えば、それは単に文章力を養うためではなく、幼いわたしのための小さなセラピーだったように思う。
わたしのような特性を持つ人間は、繰り返すが、自己肯定力に乏しい。空気を読めなかったり、あるいは読みすぎたり、独自のルールからはみ出すことができずに「失敗」をすることが多いからだ。そして自己肯定力が低くなると、自分には何もない、ときには生きている意味すらないと思うまでに至り、落ち込む。そして、暗いオーラを撒き散らして、周囲に迷惑をかける……。
いつだったか、教育学者のS先生と雑談をしていると、「自己肯定感の低い人はねえ、周りが褒めたりなだめたりしなきゃいけないから、とにかく面倒臭いんです。重いんですよ(笑)。そうじゃなくて、自分の機嫌は自分でとるのが大人でしょうね。多少は自己肯定感が“高すぎる”くらいがちょうどいいんですよ。そう、軽やかにね」という話になったことがある。いやはや、まったくその通りで、わたしは顔を赤らめた。
いま、世の中が暗く、とかくイレギュラーなことの連続で、発達障害という特性をもつ人々にとって(もちろん辛さの種類は千差万別。いまはどんな人でも苦しい)、かなりしんどい状況にある。ところが皮肉なことに、ヘルプを出したい今だからこそ、「わたし、辛いんです!」「こんなふうに体調が悪くて」などと言い出しづらい側面があるように感じている。なぜなら、みんな一様に辛いことを知っているからだ。
「せんせい、あのね。」を、ふと思い出す。思いを書き、それを誰かが受け止めてくれて、ささやかな自己肯定感をもたらしてくれた、あのシステムを……。しかし、大人である私たちは、「自己肯定感を高めたいから、読んで。感想を頂戴!」というわけにはいかない。S先生なら、きっと「面倒くさいなあ(笑)」と笑うことだろう。
したがって、だれか好きな人、信頼できる人、あるいは好きだったけれど他界してしまった人などを思い浮かべて、「◯◯さん、あのね。」で始まる文章を書いてみるのはどうだろうか? とにかく書いてみることで、思いのほか、自分では意識していなかった感情が溢れて出てくるもの。だから、書きながら「ふむ、いま自分はこう悩んでいるのか。こんなことが不安なんだな」と、頭を整理することができる。書いているうちに涙が出てくることもあるかもしれないが、それも立派なセルフセラピーだ。
もちろん、書いた文章は、そっと引き出しやPCファイルのなかにとどめておこう。数年後、見返すと新たな気づきがあるかもしれない。
わたしも、今晩は須山先生にあてて「せんせい、あのね。」と、やってみようか。聞いてもらいたいことが、山ほどあるから……。
※画:野中ユリ 「二つの部屋」